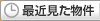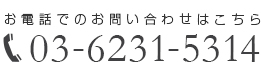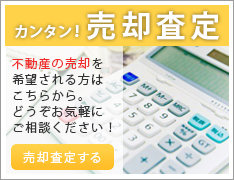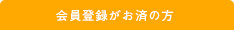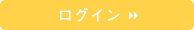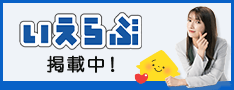不動産売却をおこなう際、税金や法律、責任について知っておかなければなりません。
売却活動を始める前に知っておかなければ、売却後にトラブルになってしまうリスクがあります。
この記事では、瑕疵担保責任から契約不適合責任へ改正された背景や違い、今から不動産売却をおこなうポイントについて解説します。
民法改正によって瑕疵担保責任から契約不適合責任へ!その背景とは?
契約不適合責任とは、不動産の売買契約締結後に契約内容に適合しない部分が見つかった場合、売主が責任を負うというものです。
2020年4月の民法改正により、瑕疵担保責任から名称が変わりました。
この民法改正には、さまざまな理由があります。
まず、わかりやすく身近な民法にするためです。
日常生活にて「瑕疵」という言葉は使わないため、読めない方が多いことから改正に至りました。
次に、買主が請求できる権利や瑕疵が増えたことです。
とくに瑕疵は、隠れていないものでも責任を追及できるようになりました。
このように責任の名称のみならず、概要も民法改正によって変わりました。
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?比較しながら解説!
契約不適合責任と瑕疵担保責任には、名称以外にも違いがあります。
まず法的性質で、契約不適合責任は「売買契約の内容に適した物件を引き渡す」という責任を売主が負うことになります。
対して瑕疵担保責任は「売買対象の物件を引き渡すこと」が売主の責任となるため、瑕疵があった場合には買主が不利になっていました。
責任を負う対象では、契約不適合責任は契約内容と合致しない箇所なのに対して、瑕疵担保責任は隠れた瑕疵に対してという違いがあります。
また、買主が請求できる権利も異なります。
前者は追完・代金減額・損害賠償・契約解除の4つを請求できるのに対して、後者は損害賠償と契約解除のみしか請求できません。
これでトラブル回避!契約不適合責任のもとで不動産売却をするポイントは?
契約不適合責任のもとで、不動産売却をするためにはどのようなポイントに気を付ければ良いのでしょうか。
まず、既知の欠陥は必ず契約書に記載することです。
契約不適合責任が対象となるのは「契約に適合しない箇所」なので、あらかじめ契約書に記載しておかないと後々トラブルのもととなってしまいます。
次に、設備に関する責任は負わないことです。
中古の物件では、経年劣化によって設備の故障や不具合が生じていることが多くあります。
想定外の責任を追及されないためにも、設備に関しては責任を負わないと決めておくことが必要です。
また、免責特約を設けることも大切です。
これは売却後3か月と期間を設けることが一般的で、通知期間の特約を設定しなければ、契約締結後10年が時効期間となります。
まとめ
売主が契約不適合責任を負うことになりましたが、後々トラブルにならないために瑕疵を契約書へ記載しておくことが大切です。
しかし売主自身を守るためにも、設備の欠陥は責任を負わないことや瑕疵の通知期間を設ける必要があります。
のちのトラブルを防ぎつつも、自身を守れるよう契約書に瑕疵を記載しましょう。
テイクワン株式会社では、葛飾区・江戸川区の新築戸建て・不動産を豊富に取り扱っております。
住まいに関するお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
テイクワン株式会社 メディア 担当ライター
弊社では、葛飾区・江戸川区の不動産情報をご紹介しております。葛飾区・江戸川区周辺で新築戸建てなどのお住まいをお探しの方は、ぜひ当社にお問い合わせ下さい。様々なご希望に合った物件探しのお手伝いをするため不動産に関する記事をご提供します。